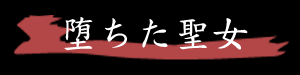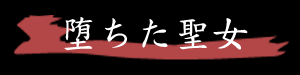2
『シャルロット…、光の司祭の孫娘よ』
「だれでちか?」
『ワシの名はベルガー。お前達が仮面の道士と呼ぶものだ』
その声は穏やかで静かに響く。おじいちゃんに似てるとシャルロットは思った。
『お前に問おう。何故お前は生きるのだ?』
「それは…」
『答えられまい。何故なら生きることに理由など無いからだ』
「そんなコトない!!
おじいちゃんは「ひとをいつくしむこと」がいきることっていってたよ?」
『そして、人は愛し合い世界を育んで行く。奴はお前にそう教えたのだろう?』
「なんで、それを?」
『当然だ。ワシとて昔はウェンデルの司祭だったのだ。
そしてお前の祖父とは親友だった。奴の口癖なら今でも憶えておる』
「ならなんで、こんなひどいことをするの?
おじいちゃんのおともだちだったんでしょう?」
『ワシは酷いことなどしておらん。
むしろその逆で世界を救いたいと思っておるのだ』
「せかいをすくう?」
『そうだ。だからこそ、ヒースもワシの考えに賛同し協力してくれているのだ』
「うそ!!おまえはそうやってヒースだけじゃなく、
シャルロットもだますきなんでちね!?」
『騙すとは人聞きの悪い。ワシは仮にも聖職者。嘘はつかん。
シャルロットよ、ワシはお前にも協力して欲しいのだ』
「きょうりょく?」
『世界を救う為には、全ての存在を『死』で救済せねばならぬ。
人は生きる限り苦しみを味わう。ワシにはそれが我慢ならぬのだ』
確かにそれは一理あるかも知れない。でも…
「たしかにくるしみはあるよ。
でもたのしいこと、うれしいことだってたくさんあるんだよ?
しんじゃったら、ぜんぶなくなっちゃうんだよ?」
少女の瞳には大粒の涙。
普段は明るいムードメーカー。
でも、その心の奥には光に包まれた慈愛の心が備わっている。
その優しさが少女に涙を流させるのだ。
『ならば今一度問おう。
お前の両親は何故死んだのだ?』
「!?」
『ワシは知っておるぞ。お前の両親は人とエルフ。
種族の違いで愛し合えないことを悲観して、禁断の呪法に手を出したのだったな。
そして、それが原因で寿命が縮み早世した…』
「それはおたがいをたいせつにおもいあっていたから!!
それにふたりはしぬまでしあわせそうだったって…ようせいおうのおじいちゃんが…」
『おぉぉ、可哀そうに…。シャルロット、お前は騙されているのだ』
「だまされてる?」
『それは幸せなどではない。生を育む愛が生み出した「悲劇」なのだ』
「そ、そんなこと…」
『それだけでは有るまい。その後、お前はどうなった?』
「シャルロットは、そのあとおじいちゃんにひきとられて…」
『そうだったな。だが、両親のいなかったお前はずっと寂しかったのではないか?』
「!!」
そうだ。ずっと寂しかったんだ…
頑なな心が、核心をつかれ震えた。
その瞬間、今まで我慢してきた想いと過去が堰を切ったように決壊する。
唯一の肉親である祖父はウェンデルの光の司祭。
仕事が忙しくてシャルロットが遊んで欲しい時も、
寂しくて一人で部屋で泣いた時もそばに居てはくれなかった。
その寂しさを紛らわす為に、明るく楽しい子でいようと振舞い気を引こうとした。
おしゃべりな饒舌も、そうやって身につけたものだった。
でも心の中ではいつも思っていたのだ。
さびしい…。シャルロット、さびしいよ…。きづいて、ここにいるの、きづいて…
たすけて、さびしいよぉ……、シャルロットをたすけて!!!
邪悪なオーラに呼応するように…
少女の澄んだ青い瞳から輝きが失われ、表情は虚ろなものに変化していく。
それでも語りかける穏やかな声。
『だが誰が悪い訳でもない。その全ては生きる事によって発生した悲劇なのだ』
「いきること…、はっせいした…ひげき」
『そうだ。お前の両親が死んだのも、
お前が寂しさに泣いたのも全てが『生の苦しみ』なのだ』
「パパ、ママ…。それに…ずっとさびしかったのも…」
『だがシャルロット、
お前ならそんな生の苦しみから全ての者を開放することが出来るのだ』
「シャルロットが…みんなを…すくう…」
少女の瞳が赤色に変化し始める。
虚ろな表情を浮かべ、抑揚の無い声で仮面の道士の言葉を反復して紡ぎ始める。
『全ての生者に救済を』
「すべての…せいじゃに…きゅうさいを…」
『生ある者に死の安らぎを』
「せいあるものに…しの…やすらぎを…」
『受け入れよ、死の福音を』
「うけいれよ、しのふくいんを」
『受け入れよ、死の快楽を』
「うけいれよ、しのかいらくを」
その瞬間、体が急激に快楽に包まれて全身が絶頂を連続で迎える。
シャルロットがもしセックスを経験したことがあったのならば、
それを極上にしたような感覚だと思ったことだろう。
細胞の一つ一つが停止して、別の存在に書き換えられているのが分かる。
「ふぁぁぁ!んん…これ、すごいぃ…』
闇が纏わりつき、シャルロットの心と体を犯していく。
でも不快じゃない。むしろ、心地良い。
体の感覚が失われていくのに、心だけがゾクゾクと快楽に打ち震えるのだ。
デス・エクスタシー(死の快楽)と呼ばれる呪法が少女を…
死を司る聖女へと変えていく。
「こわいのに、こわいのにぃ…!だめぇ…、ふにゃぁぁ…、きもちいいよぉ…
しんじゃう…、シャルロット、シャルロット……しんじゃぅ、らめぇぇぇぇぇ!!」
ビクン!!ビクン!!と体が跳ねていく。
そして少女の体は絶頂を迎えるたびに急成長する。
背が伸びて、手足も伸び、腰がくびれていく。
胸も成長して乳房がふくらみ、揉み心地の良さそうなサイズに変化していく。
年頃の女性の象徴的な様相に変化した部位はさらなる快楽を生んで、
少女をさらなる高みへと昇らせていく。そして…
「ふぁぁ…、あぁ…、もう…だめぇ……」
「ひぐぅっ…!!」
ビクッ!……
…少女の人間としての時間はそこで終わった。
程なくして…
存在を歪めらた少女は虚無の表情で、自らの絶対の主の呼びかけに答えた。
『さぁ、聖女よ。目覚めの時だ』
『はい…、仮面の道士…様…』
少女は静かに身を起こし立ち上がった。
幼かった容姿はそこになく、本来の年齢を思わせるそれに変わっていた。
膨らんだ乳房、くびれたウエスト、艶のあるヒップ、どれもが官能的な美しさをかもし出す。
だが面影は確実に残っており、あの少女が美しく成長すればこのようになるだろうという
理想的なプロポーションを形成している。
『私は『堕ちた聖女』。
全てを死で救済する仮面の道士様の忠実なるシモベ…』
手を広げるようにして、そう呟き…、その表情に邪悪な笑みを浮かべる。
それは宵闇に濡れる邪悪なる聖女、闇のシモベそのもの。
『はぁぁ〜、あのがきんちょがこんなになるなんて驚きですネ!!
ささ、このままではいけませんなぁ、こちらにおいでなさい。
仮面の道士様に謁見するに相応しい姿に私がコーディネートしてあげまショ!』
『はい…』
虚ろな様相で頷くと少女は言われるままに死を喰らう男についていく。
施される化粧。
青色のアイシャドウをスッとさし、同じく青色の口紅が官能的な唇を彩る。
更には淫靡なフォルムの黒色の司祭服に身を包む。
全てを抵抗すること無く受け入れ、少女は『聖女』に変わっていく…
|